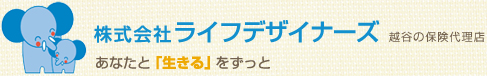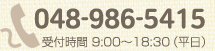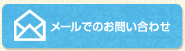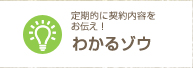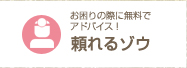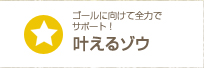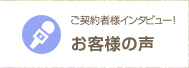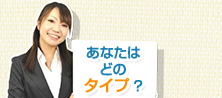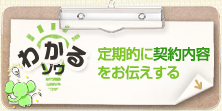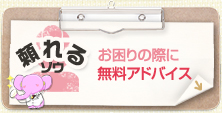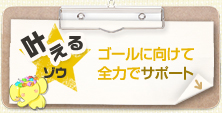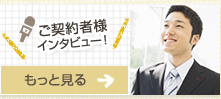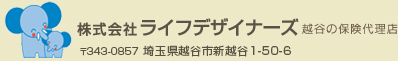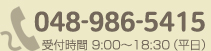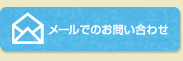HOME > 新着情報
【新聞記事より】睡眠改善の3法則
2017/04/17
眠りで悩む人は多い。企業などの睡眠研修を担当する作業療法士で、民間資格の睡眠健康指導士の菅原さんによると、「起床後4時間以内に光を見る」「起床後6時間経ったら仮眠タイム」「起床後11間経ったら体を動かす」の3つの法則で睡眠が改善するという。
まず、「光を見る」。夜になると脳からメラトニンが分泌されて眠くなる。朝、強い光を見ると分泌が止まるため起きたら光を見る事が大切だ。
次に「仮眠」について。目覚めてから最初の眠気はやって来るのは8時間後。朝7時に起きたなら午後3時頃だ。「この時間に眠くなりやすい人は、昼休みの時間に仮眠を取るといい」と菅原さんは言う。
「体を動かす」について。睡眠中は体温が下がる。起床後は体温が上がりだし、11時間で体温が最も高くなる。このタイミングで運動するとさらに体温が上がり、眠るときスムーズに下がりやすく寝つきが良くなる。
起床後、8時間で眠気。なるほど…14時前後に睡魔がやって来るのには理由があったのですね。昼休みに仮眠をとって、午後の仕事もスッキリ出来、夜もグッスリ寝れるとは一石二鳥!ぜひ習慣にしたいですね♪
【新聞記事より】「便潜血検査」で早期発見
2017/03/13
大腸がんは子宮頸がんと並んで検診による早期発見が最も有効なタイプで、早期のうちに手術すれば100%近く治ります。最近では内視鏡による切除も可能となり、入院期間も数日ですみます。
大腸がん検診は、便の中に含まれる微量の血液を調べる「便潜血検査」という簡単なものです。費用もほとんどかかりません。早期発見には毎年検査を受ける事が重要です。検査では通常、2日にわたって便を取ります。がんがあっても、1回の採便で見つかる確率は45%程度と高くありませんが、2回調べれば70%が見つかります。大腸がんは進行が遅く、3年くらいは無症状です。2年検査を受ければ97%のがんを見つけることが出来ます。
実際には、その後の精密検査(内視鏡検査)での見落としもありますので、これほど高い率にはなりませんが、毎年検査を受けていれば、大腸がんの8割を早期に発見できるとされています。
残念ながら、日本人の便潜血検査の受診率は米国に半分程度にとどまっています。がんは早期発見で治る時代なので、自分の体のチェックを怠らないようにしましょう!
【新聞記事より】「冷え症」は万病のもと
2017/03/6
冷え症は女性だけでなく男性も少なくない。まだらめクリニックの斑目院長が6千人を対象に行った調査では、強い冷えで悩む人の10人に1人は男性だったという。冷えは自覚するしないにかかわらず、様々な病気の引き金になったり、症状を悪化させたりすることに繋がる。
冷えが不調をもたらす原因の一つは自律神経にあると考えられている。斑目院長は「自律神経のうち副交感神経が優位になると、内臓の動きが活発化する。しかし冷えはこの副交感神経の働きを抑え込んでしまう」と話す。逆に、冷えで活発化する交感神経は多くの内臓機能を低下させたり、筋肉をこわばらせたりする動きがあるので、全身に影響が出るというわけだ。
また副交感神経は体内の免疫機能を担ってるリンパ球の動きとも密接な関係にある。冷えによる副交感神経の低下は免疫力の低下をもたらし、感染症にかかりやすくなるだけでなく、さらにはがんも発症しやすくなるという。
体温が低い人が多いですよね。体温が1度下がるにつれて30%免疫力が下がるそうです。まずは出来ることから…仕事の合間にストレッチをして血の巡りを良くしましょう!
【新聞記事より】運動はバランスが大事
2017/02/20
健康のための運動は、量(歩数)と質(強度)のバランスが大切だ。東京都健康長寿医療センター研究所の青柳さんによると「1日8000歩・中強度の運動20分」が健康にいい運動法だと結論づける。中強度の運動とは、うっすら汗ばむ程度の速度きやぞうきんがけ、ラジオ体操などで「なんとか会話はできるが、歌は歌えないくらいの運動」(青柳さん)を指す。ただし、青柳さんは「8000歩・20分」を超えると、運動しすぎによる弊害が出てきやすくなると指摘する。
やりすぎはよくないが、ある程度の歩数と中強度の運動時間まではそれらが増えるに従い、予防できる病気が増えるという。なぜか。「運動をすると代謝が良くなり、脂肪が燃焼したり、体温が上がりやすくなっりするから」と青柳さん。加齢とともに体温は下がる。それは筋肉の量が減る事が大きい。運動、特に筋肉量を増やす中強度の運動は、体温アップにつながり、病気の予防にもなる。
1日・1万歩と聞いていたが、多すぎると弊害があるとは…。そういえば、歩き過ぎはかかとを傷めると聞いたことも。何事もほどほどが大切ですね。
【新聞記事より】ナッツで死亡リスク減?
2017/02/13
カシューナッツやクルミ、アーモンドのナッツに、死亡リスクを減らす効果があるのをご存じだろうか。
「ハーバード大学の研究者らが10万人以上の米国人男女を対象に20年以上追跡調査した結果、1日に28g以上のナッツを週2回以上食べている人は、まったく食べていない人よりも死亡リスクが約15%も減少することがわかりました」と東海大学・川田教授は語る。
死因別に解析した結果によると、がん、心臓病、呼吸疾患による死亡りすくが明らかに低下していることもわかったという。この結果が日本人にそのまま当てはまるかどうかはわからないが、ナッツには健康効果があると考えてよいだろう。ナッツ28gというと、ほんの一握り程度の量。小柄な女性の手のひらに十分に載るくらいだ。これを週に2回以上食べればよいのだから、そう難しくはないだろう。
ダイエット中の間食にもナッツは良いと言われてます。健康やダイエットの為に食べるナッツですが、高カロリーなので食べ過ぎは禁物です。無塩のナッツを選ぶことも大切です。
【新聞記事より】注射不要ワクチン研究
2017/01/16
予防接種といえば、チクッと痛い注射を思い浮かべ、顔をゆがめえる人も多いだろう。だが、近い将来、「痛くない」インフルエンザワクチンが普及するようになるかもしれない。国立感染症研究所の長谷川部長らのチームが研究を進めている「経鼻ワクチン」だ。鼻の中にシュッとふきかけるだけで痛みはなく、予防効果も高いという。
インフルエンザウイルスは通常、鼻やのどの粘膜に限定的に感染し、血液を通じて全身には広がらない。今の注射によるワクチンは血液中にウイルスをやっつける抗体をつくるが、感染後すぐには効きにくく、これが完全に予防できない原因の一つだ。経鼻ワクチンは病原症をなくした不活化ウイルスに補助剤を加えたもので、鼻やのどの粘膜で免疫を直接活性化させるため、感染しにくいという。
しかも、注射だと流行するウイルスの型とワクチンの型が違うと、予防効果が低くなるが、経鼻ワクチンは型が違っていても効果が高いことが、動物実験で確かめられている。長谷川さんは「5年後の承認をめざしている」という。
せっかく打った予防接種も型が違うと感染してしまう。そこもカバーしてくれるのは有り難い。注射の苦手な子供達の為にも早期の承認を頑張って頂きたいですね。
【新聞記事より】告知で退職 冷静に判断を
2017/01/10
ガン患者の3割が現役世代ですが、会社員がガンと診断されると、約3割が離職しています。特に問題なのは、このうち約4割の人が治療が始まる前に会社を辞めてしまっている事です。病気が治らないわけでも、副作用がつらいわけでもないのに退職してしまっているのです。
告知を受けると、心も体も大きく動揺し、一時的に極度のうつ状態になることが普通です。この状態は二週間程度続きますが、通常は徐々に平常な状態に戻っていきます。しかし、長くうつ状態が続いたり、適応障害をきたしたりすることも珍しくありません。この時期に冷静な判断をすることは困難ですから、会社を辞めるなどの重大な決断をすべきではありません。現実には、ガンが治れば、一部の例外を除いて、元通りの生活に戻り、仕事も以前と同様にできることが多いのですが、このことを本人や経営者を含めて会社全体で共有する必要があります。
ガンも治る時代となった今、治療後に今まで通りの生活をすることを前提として、戻る場所を捨てない事が大切なんですね。
【新聞記事より】睡眠とアイデアの関係
2016/12/5
斬新なひらめきやアイデアが生まれやすい時間帯はいつか。脳の働きが良くなるのは、たっぷり睡眠を取った後。つまりアイデアを考えるのには午前中がいい。「とはいえ、ゼロからひらめきは生まれない。ひらめきを生むには、それなりの準備が必要」と睡眠評価研究機構の白川代表は語る。つまり、あらかじめテーマについての情報を集め、あれこれ考えておく。睡眠中の脳は昼間の記憶を整理している。「脳は日中に仕入れた情報を取り出しやすい状態にインデックス化しておきます。そして、翌日、睡眠で改善した脳の働きによって、記憶の意外な結びつけをもたらし斬新なアイデアが生まれやすくなる。」という。
「天才的ひらめきなんて滅多にないでしょう。普通はちょっと見かたを変えることで、新しいアイデアが生まれてくる。睡眠中に脳が情報のインデックス化を行う結果、一見関係ない過去の記憶もよび起こされ、良いアイデアが浮かぶ」のだ。
確かに、あれこれ悩んで結果を出せずに寝てしまい、翌日、改めて考えてみたらあっさり結論を出せたりしますよね。睡眠中にごちゃごちゃになったデータを片づけてくれていたのですね。納得です。
【住所表記変更のお知らせ】
2016/11/14
2016年11月26日(土)
から、住所表記が変更になります。
新 〒343-0857 埼玉県越谷市新越谷1-50-6
旧 〒343-0851 埼玉県越谷市七左町2-241-1
宜しくお願い致します。
【新聞記事より】遺伝子で決まる薬の効き目
2016/11/7
同じ薬を服用してもよく効く人と効きにくい人がいる。薬は服用後に体内で代謝を受け、有効成分が病原菌を排除したり、炎症を抑えたりして効果を発揮する。用を終えた薬の成分は、肝臓や腎臓から体外へと排出される。薬の作用や排出の過程では、多くの酵素が働く。酵素の働きは、個々人に備わってる遺伝子で想定される。遺伝子は、アデニン、グアニン、ミチン、シトシンという4つの塩基が連なってできている。同じ作用をする遺伝子であっても、人によって数百塩基対に1塩基ほどが異なる場合がある。遺伝子の多型とよばれ、個人差につながる。
遺伝子の多型は病気へのかかわりやすさや、薬の効き方に関わる。結核の治療でも、薬が効きやすい人と、効きにくい人がいる。これからの多型を解析し、個人個人に対応すした治療薬や治療法を開発する試みも進む。遺伝をつかさどる遺伝子の詳細な解析が治療の進歩にもつながる。
体質は、遺伝的背景と、育ってきた環境によって左右されると言う。遺伝ではどうしょうもないですね。個人に適した治療薬・治療法の開発の試みに期待しましょう。